カツオノエボシからカツオ出汁がとれると聞いたので食べてみた

海が荒れた翌日、砂浜を歩いていると様々な漂着物を見ることができる。そのほとんどは木やゴミだが、時に面白いものが漂着していることがある。その一つが今回紹介するカツオノエボシだ。

一見、青いビニール袋のようだがその正体は猛毒クラゲで、うっかり触手に触れてしまうと刺胞と呼ばれる器官から毒針が飛び出し、そこから強い毒を注入されてしまう。刺された場所はひどく腫れあがり、焼けるような痛みに襲われるという。また、二度目刺されるとアナフィラキシーショックと呼ばれるアレルギー反応によって最悪の場合死に到る可能性もあるそうだ。
ある日、そんな危険なカツオノエボシを食べれるというツイートをたまたま発見した。
以下は2011年の奄美大島のカツオノエボシ大発生に対する某離島在住の方のツイートである。
あるカツオノエボシが食べられるというだけでも衝撃的であるのになんとカツオ出汁が出るという…果たして本体に味はあるのだろうか?調理後は何色になるんだろうか?そしてなんといっても懸念されるのは毒である。先程も述べたがカツオノエボシは強い毒を持つ、これは無毒化されるのだろうか?パっと思いつくだけでも様々な疑問が頭に浮かぶ。
現在は2016年であり、このツイートが投稿されたのは2011年と既に5年が経過していたのだがどうしても気になるので、リプライ似て質問させていただいたところ、丁寧にご返答をいただいた。
以下は質問とその回答である。
1. 地方名(奄美大島での呼び方)について
まず、電気クラゲという分類学的なグループはなく俗称である。電気クラゲというと通常は刺胞に強い毒を持つ、カツオノエボシやアンドンクラゲを指すことが多い。会話の流れからしてこの電気クラゲはカツオノエボシのことと見て良さそう?ただし、この「イラ」についてネット上で調べてみると九州の方言でアンドンクラゲを指すようである。いくつかのサイトを見たがイラとカツオノエボシとの関係性は不明である。また、残念ながら「チュンブルカイ」について有力な情報は1つも出てこなかった。しかし、クラゲに関わらず俗称は地元民の中ではよく使われているものでも、インターネット上には掲載されていない。ということが多々ある為、それだけで否定することは難しい。
2. 加熱後の変化について
カツオノエボシの体は青みがかった透明であるが加熱することによって脱色し白く(透明?)なるという。触感はコリコリになるというがこれは貝のようなイメージでよいのだろうか。未だクラゲを加熱した経験がない為あまりイメージが湧かない。
以上の2点を簡単にまとめると以下のようになる。
・カツオノエボシは奄美大島でイラと呼ばれていてカツオ出汁がとれる。
・加熱されたカツオノエボシ本体は白く(透明?)なり、コリコリした食感になり美味である。
しかし、『クラゲ大図鑑』(平凡社)によるとカツオノエボシという名の由来は「カツオがいるような海域に多く、形が烏帽子に似ていること」だそうだ。他の本でも大体同じようなことが書かれており、いずれも「カツオ出汁」という単語はどこにも記されていない。このことから少なくとも名前の由来は「カツオ出汁がとれるから」ではなく、その生態や形態にちなんだ標準和名と思われる。加えて名前の由来とは関係なしにたまたまカツオ出汁がとれたというのも出来すぎていると思うのだ。
とはいえ、実際に食べてみなければ真相はわからない。ひょっとすると本当にカツオ出汁がとれるかもしれない。丁度、カツオノエボシが家にあったので早速試してみることにした。

新鮮なカツオノエボシを水を入れた鍋に入れた後、鍋の水を沸騰させグツグツと煮込んでゆく。今更だがカツオノエボシはやり美しい。毒があると知っていても触ってしまいそうになる。
 数分後
数分後
風船部分がパンっと破裂すると思いきやそうではなく、数分の加熱でカツオノエボシの風船部分は静かに極小化。ちょっと期待はずれだったが破裂したらしたで大変なので、これでよかったのかもしれない。この時、色はまだ青いままで脱色していないが若干透明感が失われように見える。お湯の色に変化は見られない。

さらに加熱すると話通り白く脱色したが、やはりお湯の色に変化は見られなければ匂いもしない。

あれ以上加熱しても変化が見られなかったので回収。一番懸念していた毒はこの通り触っても大丈夫なようだが、摂取した場合はどうなのかこの時点ではまだわからない。この時茹で汁を飲んでみたがお湯の味しかしなかった。この時「カツオノエボシからカツオ出汁がとれる」という話は信憑性がやや低くなる。

※味がしないので汁にだしの素入れました
あとはカツオノエボシ本体の味に賭けるしかないがどうだろうか。。。よく見ると水餃子のようになっていて美味しそうである。これはもしかすると何かしらの味がするかもしれない。しかし、恐る恐る口に入れたカツオノエボシはコリコリしているだけの物体で味は旨味が無くほぼ無味であった。
今回は残念ながらカツオノエボシからカツオ出汁をとることはできなかった。ひょっとすると1匹だけでは足りなかったのかもしれないし、それ以外にも何か理由があるかもしれない。少なくとも分かったことはカツオノエボシ1匹から出汁を十分に取ることはできないということだ。またシーズンインしたらカツオノエボシの数を増やして再挑戦したいと思う。
※カツオノエボシには毒があります。捕獲、調理の際は十分に注意を払い、自己責任でお願いします。
※追記:カツオノエボシが奄美大島でイラと呼ばれているかは証拠不十分であるため削除(2023/05/21)
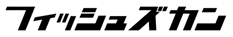








Comment
大丈夫ですか?
次は、10匹で試してみてください