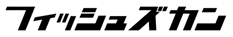ギンメダイはキンメダイに匹敵する味?

深海にはキンメダイならぬギンメダイという魚がいることを知っているだろうか?
キンメダイが全国的な知名度を誇る一方、ギンメダイを知っている人なんてほとんどいないかもしれない。
だが、それも無理もない。なぜなら、ギンメダイは底引き網で多獲されるにもかかわらず、ほとんどが廃棄または産地で消費されてしまうからだ。
そんな超ローカル魚のギンメダイだが、ネット上では割と評判が良い。どんな味の魚か確かめるべく、早速、沼津の水産会社に問い合わせて新鮮なギンメダイを送ってもらうことにした。
一文字違いだけど全く別の魚
キンメダイとギンメダイ、文字だけ見れば一文字しか違わないが、両者は分類学的に見て大きく異なる。
キンメダイはキンメダイ目キンメダイ科に属する魚で、日本のキンメダイ科はキンメダイを含めて2属4種が知られている。キンメダイ目にはイットウダイ科やヒウチダイ科、マツカサウオ科など、多くの海水魚を含む。
一方、ギンメダイはギンメダイ目ギンメダイ科という小さなグループに属しており、日本産ギンメダイ目魚類はギンメダイ科に分類されるギンメダイ、オカムラギンメ、アラメギンメ、キララギンメの4種のみが知られている。
 【キンメダイ】言わずと知れた高級魚。冬が旬の深海魚で、赤い色と大きな目はすっかりお馴染みである
【キンメダイ】言わずと知れた高級魚。冬が旬の深海魚で、赤い色と大きな目はすっかりお馴染みである
キンメダイとギンメダイは分類だけでなく形態も大きく異なる。
まず、見てすぐわかるのは体色の違いだ。キンメダイは体全体が赤色なのに対して、ギンメダイは銀色をしている。
日本産のキンメダイ科はすべて赤色だし、ギンメダイ科も漏れなく銀色をしているので、体色を見れば両グループは容易に区別することができる。
しかし、もしかするとモノクロ写真から同定するシチュエーションがあるかもしれないので色以外にも詳しく見ていきたいと思う。
 【ギンメダイ】名前はキンメダイに似るが、よく観察するとキンメダイにない特徴を持つ
【ギンメダイ】名前はキンメダイに似るが、よく観察するとキンメダイにない特徴を持つ
キンメダイにはこれといった特徴はないが、ギンメダイの下顎に注目して欲しい。なんとギンメダイとかいう魚、下顎に1対の髭を持つのだ。銀色の体色と下顎の髭は淡水魚を彷彿させるが、立派な深海魚であり、水深150~650mの深い海に生息する。
他にも地味な違いだが、背鰭が体の後半部にまで及ぶこともキンメダイとは明らかに異なる点だ。以上の点を覚えておけばキンメダイとギンメダイを間違えることはないだろう。
美味しいのに安価なギンメダイ
ギンメダイは深海に生息するため、我々の生活でお目にかかることは難しいように思える。
しかし、本種は福島県~九州の太平洋側に広く分布する魚。故に深海底引き網漁で漁獲される定番魚の1つであり、網を引けば必ずと言って良い程、入網する言わばログインボーナスのような魚である。
そのため、静岡県や愛知県などの深海底引き網が盛んな地域ではしばしば売られていることがあり、地元の漁業関係者からすれば特に珍しいものでもない。
気になるギンメダイの値段だがキンメダイとは比べものにならないほど安く、キンメダイ一匹買えるお金でギンメダイが10匹以上買えてしまう。価格が安い理由は不明だが需要が高くないというのは間違いない。そもそも味が知られていないのかもしれないし、水分の多さに起因する鮮度落ちの早さが嫌煙されているのかもしれない。
加えてギンメダイは大きくても体長20cm程にしかならない小型種だ。これはキンメダイの比較するとだいぶ小さい。大型種のオカムラギンメはキンメダイくらい大きくなるが、こちらは島嶼域の釣り漁で稀に見られる程度で供給はほぼないと言ってよいだろう。
知名度が低かったり、値段が安かったりするのを聞くと「味が悪い」と思ってしまうが、それは大きな間違いだ。結論から言うとギンメダイは超旨い。
キンメダイのような強い旨味はないものの脂の乗りが非常に良く、イマドキの舌を唸らせるのには十分なパワーを秘めている。私が言うのもおかしな話だが、そもそもキンメダイとギンメダイは別物、比べること自体が間違っているのだ。ここからはキンメダイとギンメダイを比較するのをやめたいと思う。
ギンメダイの美味しい食べ方
そんなギンメダイだが、美味しいと分かっていても入手する難易度が高かった。しかし、かつては産地以外で入手困難だったギンメダイだが、近年、日本のどこにいても簡単に深海魚を手に入れることが可能になった。
これはインターネット経由で魚を購入することが容易になったためである。実際、今回のギンメダイもネットを駆使して購入したものであり、神奈川県の自宅にいながら新鮮なギンメダイを食べることができるのはネットのおかげだ。隣県から発送されるので注文の翌日にはギンメダイを見ることができた。
ただし、ギンメダイは鮮度の低下が早い魚なので届いたらなるべく早く処理することをおすすめする。身はやや水っぽいものの、クセがないのでどんな料理にも合うので、好きなように食べるといい。
刺身

しっとりしていてうまい
高鮮度のギンメダイが手に入ったのであればやはり刺身。これを食べずしてギンメダイの旨さは語れない。ギンメダイは身の水っぽさや緩さから生食には向かないと思われがちだが、刺身はかなりの絶品。身に旨味はほとんどないが皮下の脂がしっとりと甘く、とても美味である。この値段でこの旨さは革命的だ。
焼霜造り

小型ながら皮目に脂がよく乗っている
ギンメダイは皮下に多く脂がある魚なので、これを活かした料理で食べても非常に美味しい。手軽なのは三枚に下した後に皮目を炙る焼霜造りだ。皮をバーナーで炙ると香ばしい匂いと共にじゅわじゅわと脂が湧き出てくる。これにより、旨味が乏しいギンメダイにコクと香りが加わり完全体となるのだ。
個人的にギンメダイ料理の中で3本の指に入る調理法だが、やや脂がくどく感じられ舌が飽きやすいのが難点である。
酢〆

身がしまって美味しい
ギンメダイの少ない旨味を生のまま引き出せるのが〆サバならぬ〆ギンメだ。他の料理と比較すると時間も手間もかかるが、さっぱりした味付けと皮下の脂の甘さの相性は抜群である。これを軽く炙って食べても美味しい。
塩焼き

手軽で美味しい
加熱しても美味しいのがギンメダイのいいところの一つだ。特に塩焼きはギンメダイの加熱料理の中で最もお手軽な料理。身が少し水っぽいため、焼くと少しジューシーな仕上がりになる。脂の旨さとしっとりとした身がよく合う。旨味はあまり感じなれないので醤油を垂らして食べてもよい。
煮付け

お店で食べるギンメダイは10倍増しで美味しい
ギンメダイが少し余ったので、最近、知り合った隣町の居酒屋に持ち込んだ。魚を扱う居酒屋だが、店主のギンメダイを見るのは初めてだという。確かに神奈川県では底引き網漁が操業されていないので、深海釣りでもしていなければギンメダイを見る機会なんてほとんどない。
ここではギンメダイを深海魚の定番料理である煮付けにしていただいた。身が水っぽいからって濃い味付けにする必要はなく、普通に煮て美味しい。身はホロホロと柔らかく、煮汁と脂の相性が最高である。
干物

ギンメダイの干物、これ以外にもギンザメなどが売っていた
こちらは沼津港の干物店で500円で購入したものだ。このお店ではギンメダイの他に、ヒメ、アカギンザメ、カガミダイなどちょっとマイナーな魚の干物が並んでいた。
ギンメダイ科の魚をギンメダイの唯一の欠点である水っぽさが解消されており、ギンメダイとは思えぬ味と食感を堪能することができる。ギンメダイの味を最大限楽しみたいのであればこの食べ方が1番かもしれない。
今回、幸運にも高鮮度のギンメダイを神奈川県で食べることができた。正直、食べたことがない目の魚なので、緊張していたのだが予想を遥かに上回る味で驚いた。ギンメダイ自体は地元、相模湾にも生息しており、主に深海釣りの混獲物として知られている。いつかは鮮度マックスの相模湾産ギンメダイだ食べてみたい。あわよくば自分で釣ってみたいものである。